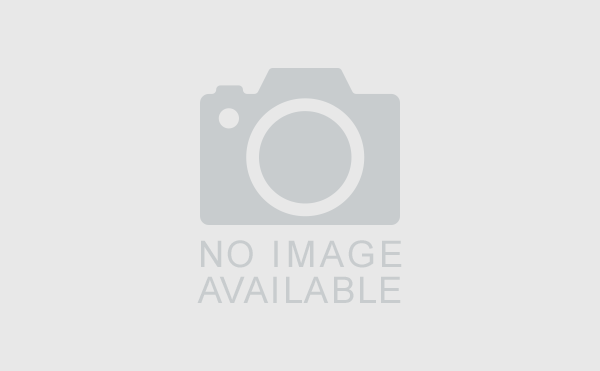アビトゥア(Abitur)
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
統一ドイツにおける旧西ドイツの一般的大学入学資格をいう。この資格を取得すると,原則として「一般的入学資格」,つまりどの大学どの学科を問わず希望するところに入学できる権利が与えられる。ただし,高等教育の大衆化が進んだ1970年以降,高等教育の収容数の絶対的な不足や医学部などの特定専門分野への志望の偏りによって,この入学資格だけで入学者の決定をすることができなくなり,資格制度の理念に反して入学者数制限(「ヌーメルス・クラウス」という。)選抜政策を採らざるを得なくなっている。
資格取得者の入学先を決めるのは,1972年に設置された中央学籍配分機関(ZVS)である。国内のすべての大学に対する入学許可を一括して扱っており,入学者と入学待機者の振り分けを行っている。選抜基準は資格取得の際の成績と入学待機期間の長さであり,資格取得の成績が低ければ待機期間の長さで補うこととなる。なお,医学部希望者(歯学希望者,獣医学希望者を含む。)の場合には,適性テストと面接試験が別に課され,その成績も選抜基準となる。アビトゥアの資格を取得するには,高等教育機関へ進学するためのギムナジウムと呼ぶ9年制中等学校に入学し,アビトゥア試験と呼ぶ卒業資格試験に合格しなければならない。この試験は,各ギムナジウムが個別に実施する場合と,州の統一試験として実施する場合があり,多くの州では前者の実施形態をとっている。先に述べた高等教育の大衆化が進む前は,このアビトゥア試験の成績によって一般的大学入学資格としてのアビトゥア資格が得られたが,現在では,アビトゥア試験の成績とギムナジウム最終2年間の在学成績との総合成績によって資格が与えられている。アビトゥア試験では,①言語・文学・芸術,②社会科学,③数学・自然科学・技術,④宗教,⑤体育,の中のいずれか3領域から4科目を選択する。うち2科目は,日本の高校における選択科目に相当する,重点コースの履修科目から選択しなければならない。