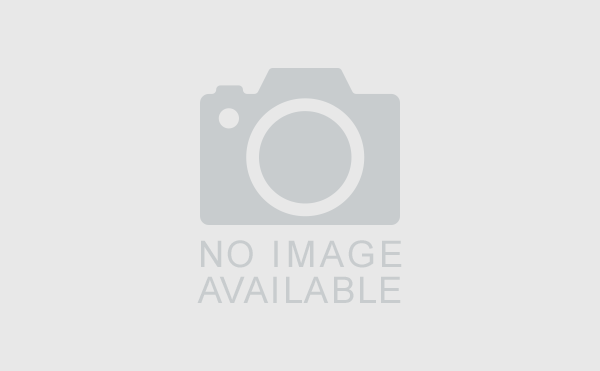代替科目
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
大学入学者選抜試験における学力検査の実施教科・科目については,一般に国語,社会,数学,理科,外国語の5教科の全部又は一部につき,それぞれ科目を定めて解答させることが原則となっている。しかし,商学,エ学,農学,水産学,家政学,看護学等に関する大学・学部で,その目的,特色,専門分野等からみて適当と認められる場合には,上記の教科の一部に代えて,職業に関する教科を出題し,又は社会,数学若しくは理科の科目に職業に関する基礎的・基本的科目を加え,選択解答させることが望ましい。また,高等学校の職業教育を主とする学科の卒業者のための職業に関する科目の出題に当たっては,職業教育を主とする学科の卒業者が普通教育を主とする学科の卒業者に比べて不利にならないよう,特に考慮するものとする(大学入学者選抜実施要項第4の1),とされており,これらに基づき,一般の科目に代えて実施される科目が,通常,代替科目と呼ばれている。
このため,代替科目については,例えば,「職業教育を主とする学科の卒業生に限る」など受験についての制限がある場合が多い。
大学入試センター試験においては,どの科目を受験するかは受験者の自由であるが,高等学校の職業教育を主とする学科の卒業生を考慮し,数学Bにおいて「数学II」の代わりに「工業数理」,「簿記会計I・II」を受験できるようになっている。(大学入試センター試験を利用する大学の個別学力検査の実施に当たっても,高等学校の職業教育を主とする学科の卒業者のため,職業に関する基礎的,基本的科目を出題し,選択解答できるよう配慮することが望ましい(同要項第10の1)とされている。)