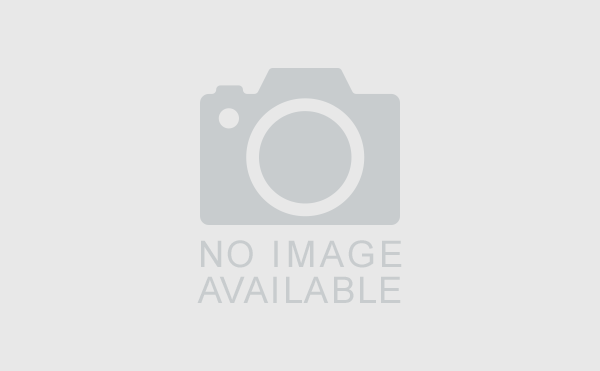傾斜配点方式
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
国公立及び一部私立の大学・学部が実施する入学者選抜試験において,その教育目的,特色,専門性等に応じて,大学入試センター試験の各教科における配点に軽重をつけて選抜に利用する方式をいう。新たに定められた軽重のついた配点を傾斜配点という。教科間の配点に軽重をつけると傾斜が現れることから,傾斜配点方式と名付けられた。各大学・学部は,大学入試センター試験総合点の配点と個別試験総合点の配点との配点比,重視する教科等を考慮して各教科の傾斜配点を決めている。
具体的には,大学入試センター試験5教科の配点(国語200点,数学200点,社会100点,理科100点,外国語200点)のそれぞれに対してある倍率を掛けて,これを新たな配点として入学者選抜に利用する。すなわち,当該大学受験者の大学入試センター試験総合成績は,大学入試センターで採点されたその受験者の各教科得点に,上記倍率を掛け合わせて合計したものとして評価される。共通第1次学力試験の発足当時には,5教科の配点はすべて200点で,教科間の重みに差はなかったが,昭和56年度の入学者選抜においては,すでに国立23大学71学部・公立10大学17学部が教科間の配点に軽重をつけて利用している。
この方式は,傾斜配点の高い教科を得意とする志願者を集める効果がある。したがって,ある大学・学部が従来の傾斜配点を変更する場合には,受験者層が教科学力からみて大きく変化することがある。その場合には,当該大学・学部による入学者の追跡調査などの対応が重要課題となる。