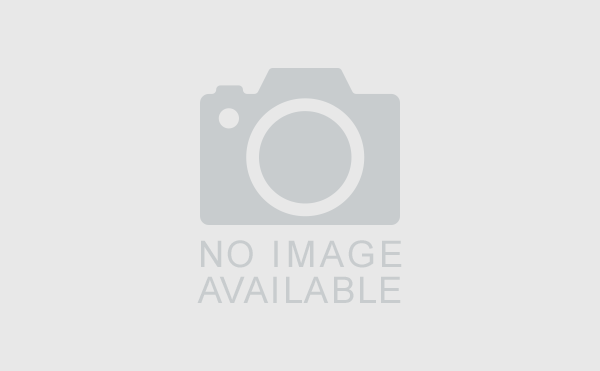大学入試センター
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
昭和52年5月の国立学校設置法の改正(国立学校設置法第9条の7)により,各国立大学と協力して実施する共通第1次学力試験の試験問題の作成など一括して処理することが適当な業務を担当するとともに,大学の入学者選抜方法の改善に関する調査研究を行うことを目的とした国の機関として設置された。
その後,臨時教育審議会(昭和60年6月答申)により,偏差値偏重の弊害是止の観点から,入学志願者の個性・能力・適性等の多面的な判定や,国公立のみならず,私立も含めた各大学の選抜方法の改善に積極的に寄与するものとして,共通第1次学力試験に代わる新しいテストの創設の提言が行われ,この提言を受けて,昭和63年5月の法律改正により,大学入試センター試験が実施されることとなり,次の3つの業務を行う機関となった。
(1)大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験(大学入試センター試験)の問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務
(2)大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査研究
(3)大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供
組織については,所長・副所長2人のほか,管理部(3課),事業部(3課),研究開発部(7研究部門)で構成され,大学入試センターの事業計画その他の管理運営に関する重要事項について審議する「評議員会」,「運営委員会」をはじめ「評価委員会」,各種の「専門委員会」等が置かれている。