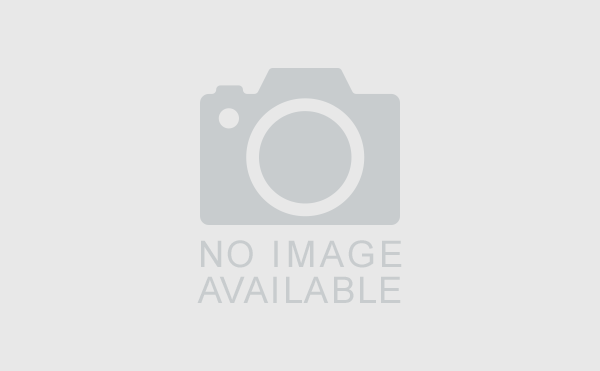大学入試センター試験
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
大学入学志願者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを目的として,各大学が大学入試センターと協力して同一の期日に同一の試験問題により共同して実施するもので,各国公私立大学がそれぞれの創意工夫に基づき,この試験を適切に利用することによって受験生の能カ・適性等を多面的に判断する資料となることを目指している(大学入試センター試験実施要項1)。
昭和54年度入学者選抜から実施された共通第1次学力試験は,難問・奇問がなくなり,高等学校教育に沿った出題がなされるようになったことなどの評価を得たが,一方,共通第1次学力試験が一律に5教科5科目利用とされていたことなどにより,大学の序列化が顕在化し,また,国公立大学のみの入試改善にとどまるなどの問題が指摘されるようになり,臨時教育審議会(昭和60年6月答申)は,この弊害是正の観点から,受験生の個性・能力・適性等の多面的な判定や,国公立大学のみならず,私立も含めた各大学の選抜方法の改善に積極的に寄与するものとして,共通第1次学力試験に代わる新しいテストの創設を提言した。
この提言を受け,文部省の大学入試改革協議会において,具体案が検討され”昭和63年2月の最終報告「大学入試改革について」に基づき実施準備が進められ,平成2年1月に第1回試験が実施された。
この試験は,共通第1次学力試験とは異なり,国公私立のすべての大学が利用することができ,その成績の利用方法も各大学の自由であるところに特色がある。
平成4年度の大学入試センター試験利用大学は,国公立大学は全大学・学部,私立大学は32大学46学部で,私立大学の利用が次第に増加している。新たにこの試験を利用した大学からは,オールラウンド型など従来とは異なるタイプの学生が入学するなど学生の多様化が図れたこと,受験生が全国的に広がり,増加した,などの反響が寄せられている。