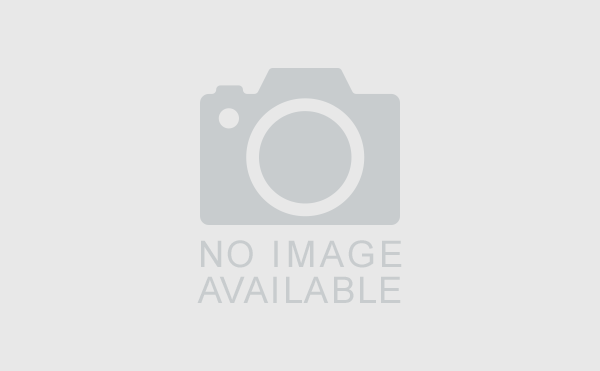第2次試験のガイドライン
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
国立大学協会は,共通第1次学力試験の実施に先立ち,長年にわたる検討を行い,その結果を報告書としてまとめ発表しているが,昭和51年3月の国立大学入試改善調査研究報告書で,共通第1次学力試験と第2次試験を組み合わせて入学者の選抜を行う場合の第2次試験の在り方について,その形式,意義及び注意点等を述べているものである。
主な内容としては,第2次試験は,①各大学・学部が自主性をもって実施すべきであり,出題は共通第1次学力試験に課されていない科目に限るカ、同一科目で行う場合も,論文形式に限るよう配慮の必要があること,②出題に当たっては,科目数・出題量を少なくすること,③学部・学科の特色によっては,面接,実技等のみで充分であること,④共通第1次学力試験の成績を推薦入学の資料として利用すること,⑤難問・奇問を避けること,などが示されている。
また,共通第1次学力試験と第2次試験との関連について,①両者の成績を適正に総合して合否判定を行うこと,②2段階選抜を行う場合は,入学定員の少なくとも3倍程度で行うこと,などが示されている。
その後,共通第1次学力試験は大学入試センター試験に移行されたが,国立大学協会は昭和61年6月の総会において,「大学入試センター試験を共通第1次学力試験改善の延長として受け止める」として了承し,昭和63年6月の総会では,「大学入試センター試験と第2次試験との適当な組み合わせにより国立大学の入学者選抜を行う」ことが決定されている。