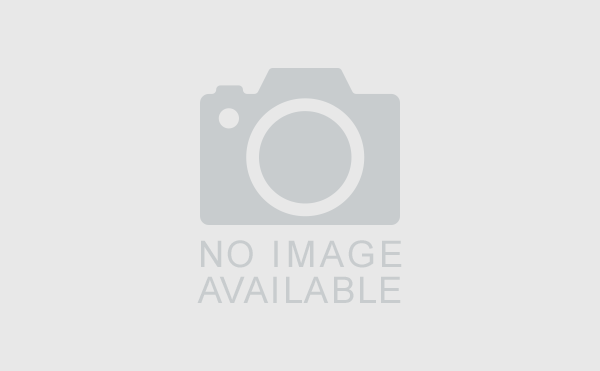1期校・2期校制
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
新制国立大学の入学者選抜については,国立大学を1期校と2期校の2グループに分け,昭和24年度(1949年)だけは,国立学校設置法が5月31日に公布された関係で,1期校は6月8日から,2期校は6月15日から,翌年度からは,1期校は3月初句に,2期校は3月下旬に設定され,一斉に実施された。この方式は,昭和53年度(1978年)まで続けられ,共通第1次学力試験による入学者選抜が実施された昭和54年度から廃止された。
どの大学を1期校とするか,2期校とするかは大学入学者選抜実施要項の別表で定められ,30年間ほぽ固定されていた。このことから,大学の区分として1期校,2期校の呼称が生まれた。
この1期校,2期校の区分については,①法学部をはじめとして,文,教育,理,医,薬,歯学部において,著しく偏っている,②地域的にも不均衝,③2期校における出願者数に対する実受験者の割合が極めて低い上,入学辞退者も多い,④国立大学間の格差を示すような社会的通念が定着化した,⑤高等学校において1期校への進学率の優劣をもって学校が評価される傾向,など多くの問題点が指摘されてきた。このため,国立大学協会において,共通第1次学力試験の実施についての検討と併せてその改善について検討された結果,これを廃止することとなったものである。