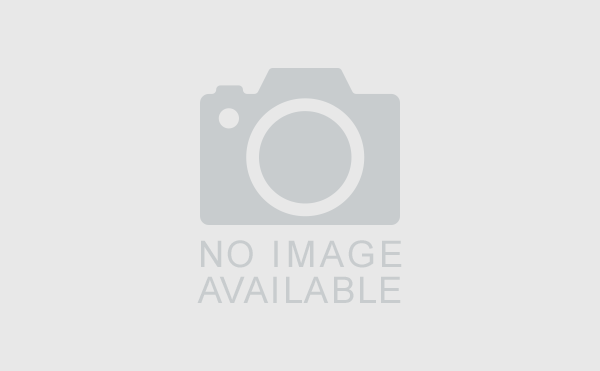自己採点方式
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
共通第1次学力試験と第2次試験等との組合せにより合格者を判定することとしていた従来の国公立大学の入学者選抜において,共通第1次学力試験の受験者が,受験後大学入試センターが①試験終了直後に発表する正解及び配点と,②第2次試験の出願受付開始前に発表する試験実施結果の概要(平均点等)により,自己の試験のおおよその得点と受験生全体に占める自分のおおよその位置付けを推定し,それをーつの参考として最終の志望(第2次試験の出願先)を決めていたことをいう。
これは,共通第1次学力試験制度の実施と同時に,従来の1期校・2期校制が廃止され,国立大学の試験期日が一元化されたことにより,高等学校側から受験の機会が1回に減少することに対して,適切な進路選択ができるよう何らかの措置を講じてほしいとの要望があったこと等を考慮して,導入されたものである。
その後,昭和62年度に国公立大学の受験機会の複数化が実施されたため,これが廃止されることになり,同年度は各国公立大学の出願期間が,共通第1次学力試験の受験前の1月初・中旬に設定された。
しかしながら,高等学校側から従来どおりの日程に戻すよう強い要望があり,昭和63年度から,自己採点方式とは言われなかったが,共通第1次学力試験受験後に出願する方式に戻された。(このときから,大学入試センターからの発表は,正解・配点は試験終了直後,実施結果の概要(平均点等)については2月中旬となった。)
大学入試センター試験においてもほぼ同様に,正解・配点については試験終了直後,平均点等統計数値については,2月初旬に発表を行っている。