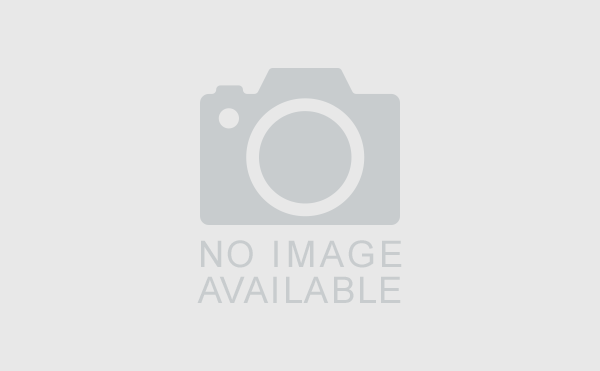臨時教育審議会
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
教育をめぐって様々な問題が起き教育改革について国民の深い関心が寄せられる中,昭和59年8月成立した「臨時教育審議会設置法」に基づいて内閣に設けら
れた審議会。社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現の緊急性にかんがみ,教育基本法の精神にのっとり,その実現を期して各般にわたる施策につき必
要な改革を図ることにより,同法に規定する教育の目的の達成に資することが設置目的とされた(同設置法第1条)。総理大臣の諮問に応じ,教育及びこれに関連
する分野に係る諸施策に関し,広く,かつ総合的に検討を加え,必要な改革を図るための方策に関する基本的事項について調査審議することを任務とし,これら
に関し,内閣総理大臣に意見を述べることができることとされた。
委員は,25名以内で,総理大臣が任命し,任期は3年である。
昭和59年9月から,審議を開始し,3年間に次のような答申を行った。
(1)第1次答申(昭和60年6月)
①学歴社会の弊害の是正,②大学入学者選抜制度の改革,③大学入学資格の拡大など
(2)第2次答申(昭和61年4月)①高等教育の改革と学術研究の振興,②時代の変化に対応するための諸改革など
(3)第3次答申(昭和62年4月)①生涯学習体系への移行,②高等教育機関の組織・運営の改革など
(4)第4次(最終)答申(昭和62年8月)
文教行政,入学時期など
大学入試改革に関しては,第1次答申において,次のような提言を行い,これを受けて,共通第1次学力試験に代わる「大学入試センター試験」が発足した。
偏差値偏重の受験競争の弊害を是正するために,各大学はそれぞれ自由にして個性的な入学者選抜を行うよう入試改革に取り組むことを要請する。
また,現行の国公立大学共通1次試験に代えて,新しく国公私立を通じて各大学が自由に利用できる「共通テスト」を創設する。この共通テストの実施のため,
国公私立の各大学が対等の立場において利用でき,高等学校関係者が参画し得るよう,大学入試センターの設置形態や機能について検討し,その改革を進める。
これとともに,各大学の入試担当機能の強化,進路指導の改善,国立大学の受験機会の複数化,高等学校職業科卒業生などへの配慮についてもその推進を図る
(同答申第3部第2節)。