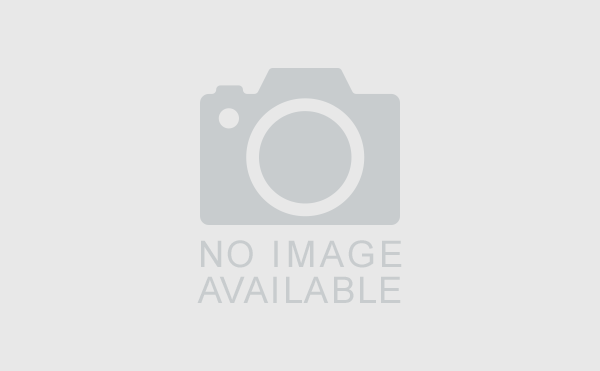受験機会の複数化
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
国立大学及び公立大学は,昭和54年度以来共通第1次学力試験を利用した入学者選抜を実施してきたが,共通第1次学力試験での良問の確保,各大学の入試改善の推進など,評価される反面,①共通第1次学力試験の成績による大学の序列化やいわゆる輪切りによる進路指導により「入りたい大学」より「入れる大学」を受験する傾向があること,②共通第1次学力試験と同時に国公立大学の受験機会が一元化したことに対する不満があること,③各大学の第2次試験の多様化がなお不十分であること等の批判があり,国立大学協会を中心にこれらの状況の打開のため昭和58年度以来改善の検討が進められた。
この結果,各国立大学・学部をA,Bの2グループに,公立大学・学部をA,B,Cの3グループに分け,A,B,Cの順で試験期日を設定して入学者選抜を実施し,受験者は,2校(公立大学のグループを含むと3校)を受験できるようにした。そして,合格者は,合格した大学のいずれかを合格後に自由に選んで入学手続きをすることができることとなった。これは受験生の負担軽減を図りつつ従来1回に限定されていた受験機会を複数化することにより,合格可能性優先ではなく「入れる大学」より「入りたい大学」へのチャレンジをより可能にし,受験生の選択の機会の拡大を目指したものである。
しかし,この制度により,昭和62年度の入学者選抜が実施されたところ,大学側,受験生の双方で不慣れであったこともあり,2段階選抜(いわゆる足切り)で大量の不合格者が出たこと,大学によっては,大量の入学辞退者が出て,入学者決定業務がかなり輻湊し,大学当局においても,また,受験者及び社会一般からも問題が指摘された。
このため,国立大学協会を中心に更に検討された結果,平成元年度から,昭和62年度の方式(以降「連続方式」と呼ばれている。)のほか,一つの大学が定員を分割して,前期と後期に分けて入学者選抜を実施し,前期に合格した者で,入学手続をした者は後期を受験できないこととする方式(以降「分離・分割方式」と呼ばれている。)を併用することとなった。
これを図示すると次のとおりである。