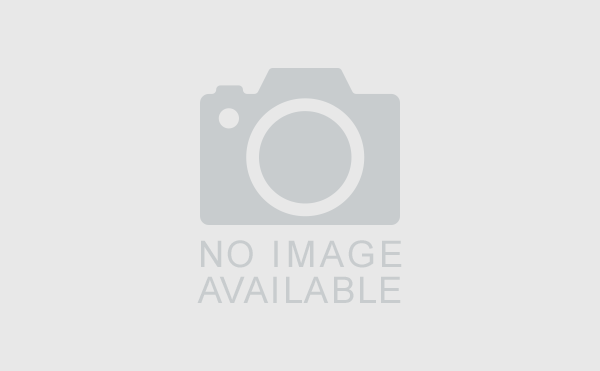学力検査
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
大学入学者の選抜は,調査書の内容,学力検査・面接・小論文その他の能力・適性等に関する検査の成績,大学が必要に応じて実施する健康診断,その他大学が適当と認める資料により,入学志願者の能力・適性等を合理的に総合して判定する方法によるものとされている。(大学入学者選抜実施要項第1の1)これら判定資料の中で,従来から最も重視されてきたのが,学力検査である。同選抜要項でも,まず,大原則として,できる限り入学志願者の負担を軽減する観点から瑣末な知識の暗記や受験技術の習得を強いることなく,特色ある選抜を実施するようにし併せて入学志願者個々の個性,適性を活かした進学を助長するよう配慮することが望ましいとした上で,次のような事項が詳細に定められている。
①高等学校学習指導要領に準拠し,高等学校教育の正常な発展の障害とならないよう十分留意すること。
②大学は,学力検査の一部又は全部を他の大学と共同し,実施することができること。
③学力検査を第1次と第2次に分け,第1次の合格者に対して第2次の学力検査を課することができること。
④国語,社会,数学,理科,外国語の5教科について実施することを原則とするが,大学・学部の目的,特色,専門分野等によっては,一部の教科を除き,又は他の教科を加えて実施することができること。
⑤学力検査実施科目は,国語,社会,数学,理科,外国語の各教科それぞれ1科目を解答させることを原則とすること。ただし,大学・学部の目的,特色,専門分野等によっては,社会・理科などの特定教科について3科目以上を出題し2科目を選択解答させ,若しくは特定の2科目を出題し解答させることができること。
⑥商学,工学,農学,水産学,家政学,看護学等に関する大学・学部で,その目的,特色,専門分野等からみて適当と認められる場合には,上記④の教科の一部に代えて,職業に関する教科を出題し,又は社会,数学若しくは理科の科目に職業に関する基礎的・基本的科目を加え,選択解答させることが望ましいこと。
⑦次の諸点に留意して,入学志願者の学習能力をできる限り合理的に検査することができるよう出題方針を立てること。
ア各種の客観式及び記述式の検査方式を適宜組み合わせて実施することが望ましい。
イ原理的,根本的なものを基礎として,これを運用して解答できるもので,それぞれの科目に関して学理的な適応性を検査できるような問題が望ましく,単なる記憶や知識のみを検査するような問題であってはならない。
ウ職業に関する科目の出題に当たっては,職業教育を主とする学科の卒業者が普通教育を主とする学科の卒業者に比べて不利にならないよう,特に考慮するものとする。