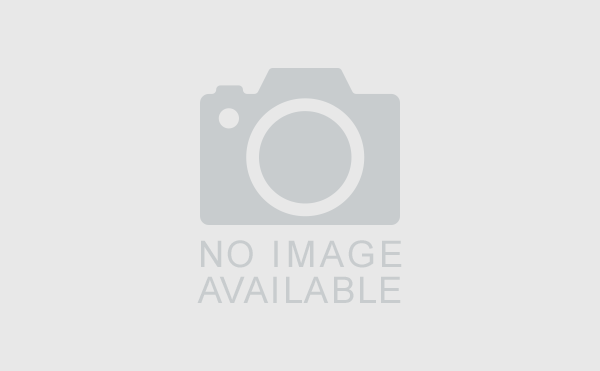客観テスト
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
試験問題の設問に対して,正答が一義的に定まっているため,正解表が与えられているかぎり,試験結果の採点及び評価に採点者の主観が入らない試験のことを一般に客観テストと呼ぶ。
客観テストの出題形式としては,解答選択肢群があらかじめ設定されていて,正答をこの中から選択して解答する多肢選択テストが多く用いられている。
客観テストの利点は,採点が採点者の主観に左右されず公平になされることて‘ある。また,正答が一義的に定まっていることから,記述式試験と異なり,採点者が人間である必要はない。マークシートを用いた機械採点(⇒OMR)により,大量の答案を迅速,正確,かつ公平に採点することができる。したがって設問をたくさん出題することが可能になり,いわゆるあて推量の効果を大幅に減らし,受験者が備えている学力の多様な側面を万遍なく評価することができる。反面,受験者の具体的な解答過程が分からないこと,マークシートの場合,正答のマークを付ける位置に注意力が要求されるといったことがある。
客観テストにおける問題の作成に際しては,出題範囲,内容,問題の量,設問の形式,配点,受験者の解答過程,解答選択肢の内容等が十分に検討されなければならない。出題の工夫により単なる暗記ではなく,深い思考力を測ることも可能である。
客観テストは,記述式試験とうまく併用することによって,その長所を一層活かし,その短所を補完することができる。したがって,各大学・学部にとって,客観テストと記述式試験とのバランスがとれた入学者選抜方法の工夫が重要課題になっている。
我が国においては,現在,大学入試センター試験をはじめ,各大学の個別学力試験の一部,公務員試験,医師国家試験等に利用されている。