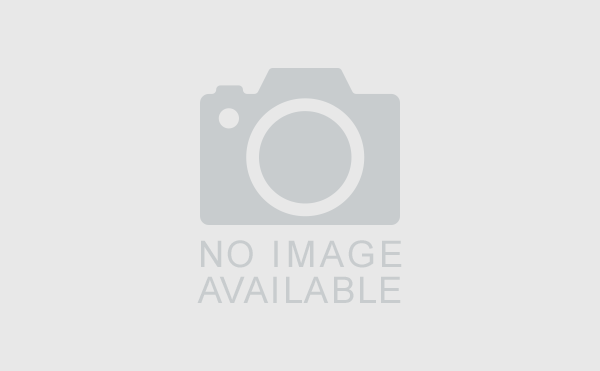旧制高等学校入試
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
旧制高等学校は,歴史的には,前史としての東京大学予備門の時代,高等中学校の時代(1886~1894年),旧高等学校令の時代(1894~1918年),改正高等学校令の時代(1919年~)に区分することができる。旧制高校の入試は,旧制の高等学校が存在した期間,以下のように単独試験単独選抜,共通試験総合選抜,共通試験単独選抜など,様々な方法が試みられたが,入学試験自体は,基本的に,学科試験,口頭試問,身体検査で構成されていた。
①1901年以前
1901年までは,高校入試は各高校独自に実施されていた。
②1902年から1907年までは,共通の学科試験で全高校一斉に実施される共通試験総合選抜方式が採用された。
③1908年から1916年までは,統一の学科試験科目で,各高校が単独で選抜を実施した。
④1917年,1918年においては,再び共通試験総合選抜方式がとられた。
⑤1919年から1927年までは,共通試験単独選抜方式が採用された。
⑥1928年から1940年までは,各校独自の出題による単独選抜方式で実施された。
⑦1941年から再び共通試験単独選抜方式が復活し,1945年まで続けられた。
⑧終戦後の1946年からは,各校独自の出題による単独選抜方式で実施されたが,1947年には「知能検査」の名で,1948年には「進学適性検査」の名で,学科試験とは別に,適性検査が課された。