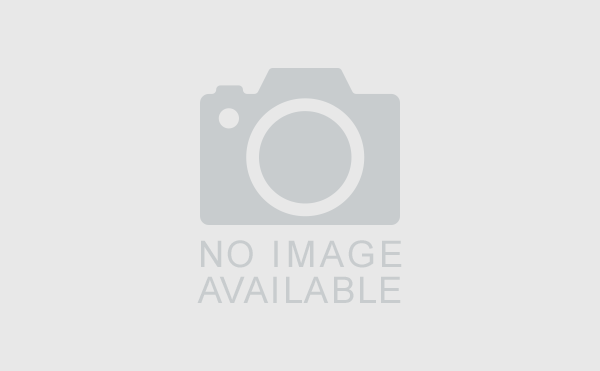共通第1次学力試験
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
大学進学者の増大,18歳人口の動態,大学改革の志向などを背景に,国立大学の入試改革に対する強い世論の高まりの中,国立大学協会が昭和46年から約6年間にわたり詳細な検討を重ね,昭和54年度入試から発足させた国立大学の共通試験制度。公立大学もこの趣旨に賛同し全大学が参加した。
きめ細かで丁寧な入学者選抜の実施,学力検査試験問題の適正化(難問・奇間の排除)及びこれを通じた高等学校教育の正常化への寄与,1期校・2期校制の廃止などを目指した。「主として入学志願者の高等学校における一般的・基礎的な学習の達成度を判定すること」を目的とし,国公立大学は,この試験の結果と,各大学がその目的,特色,専門分野等の特性にふさわしい能力・適性等を有するか否かを判定することを目的として実施する第2次試験の結果等を総合して選抜を行うこととなった。
この試験は,各国公立大学と大学入試センターが共同・協力して実施することとされ,昭和52年5月の国立学校設置法の改正により,「国立大学の入学者の選抜に関し,共通第1次学力試験の問題の作成及び採点その他一括して処理することが適当な業務を行うとともに,大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査研究を行うこと」を目的として,大学入試センターが設置された。
国語,社会(2科目),数学,理科(2科目),外国語の5教科7科目を全受験者が受験することとされた(昭和62年度から原則として5教科5科目に変更)。
平成元年度まで11回実施されたが,実施を重ねるうちに①良質な試験問題の確保,②各大学の2次試験の多様化が図られた,などの評価とともに,①原則として5教科5科目と一律的に利用されたこと等による,いわゆる大学の序列化等が顕在化し,②国公立大学のみの入試改善にとどまったことへの批判や,③国公立大学の受験機会の複数化の要請が強まった。
このような状況の下で臨時教育審議会(昭和60年6月第1次答申)により,偏差値偏重の弊害是正の観点から,入学志願者の個性・能力・適性等の多面的な判定や,国公立のみならず,私立も含めた各大学の選抜方法の改善に積極的に寄与するものとして,共通第1次学力試験に代わる新しいテストの創設の提言が行われ,これらを踏まえて文部省の大学入試改革協議会でテストの構想等について研究協議が重ねられた結果,平成2年度から,大学入試センター試験が実施されることとなった。