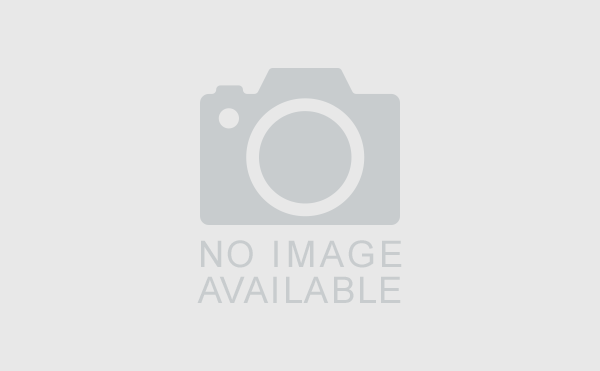大学入試改革協議会
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
臨時教育審議会(昭和60年6月第1次答申)から提言のあった大学入試改革の実施等に関し,研究協議することを目的として,文部大臣裁定により,昭和60年7月に文部省に設置された大学入試の改革に関する協力者の会議をいう。
大学の学長及び教授,教育長,高等学校長,学識経験者等約20人の協力者により組織され,小委員会も設置された。また,必要に応じ協力者以外の者にも協力を求めるほか,関係者の意見も聞くことができるとされていた。
この協議会の任務は,臨時教育審議会の第1次答申で提案された①新しいテストに関することや,②新しいテストを軸とした大学における入学者選抜方法の改善に関すること,③大学入試センターの在り方に関すること,であった。
この協議会は,昭和61年7月に「新しいテストの基本的な構想」について取りまとめ,公表するとともに,大学入試センターにおける調査検討結果をも踏まえて更に検討を続け,昭和63年2月15日に最終報告「大学入試改革について」を取りまとめ発表した。
この最終報告により,「新しいテストの具体案」と「大学入試センターの在り方」及び「高等学校における進学指導の改善策」が示された。
これらを受け,国立学校設置法の改正等が行われ,大学入試センター試験の具体化が進められるとともに大学入試センターの新しい任務として大学情報提供事業等が開始された。