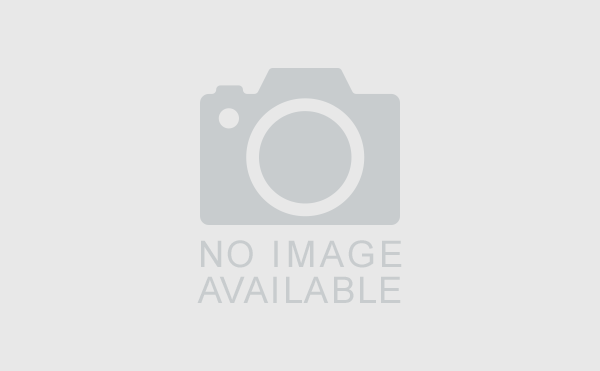進路指導
※本用語の解説は1992年に作成されたものです。
昭和52年7月に刊行された「中学校・高等学校進路指導の手引」によると,進路指導とは,「生徒の一人一人が自分の将来の生き方へ関心を深め,自分の能カ・適性等の発見と開発に努め,進路の世界への知見を深め,自分の将来の展望を持ちながら進路の選択を行い,卒業後の生活によりよく適応し,社会的・職業的自己実現を達成していくために必要とされる生徒の自己指導能力を伸ぱすことを目指して,教師が生徒に対して行う組織的継続的な指導・援助の過程である」と定義されている。高等学校における進路指導に関しては,特に,学校教育法第42条の高等学校教育の目標のーつとして,「社会において果たさねばならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的教養を高め,専門的技能に習熟させる」と定められている。
これらを総合すると,進路指導とは,生徒の能力,性格,興味等といった個人情報,及び家庭環境等の生徒を取り巻く情報を総合して,進路選択の問題に直面したときにそれを自分で解決し,将来の職業生活において満足できる人生設計ができるような能力を培わせることを目標として,教師が組織的かつ系統的に生徒を指導援助する過程ということができる。
このために教師が生徒に行う具体的な進路指導の方法としては,(1)観察,面接及び各種検査を通しての生徒理解,(2)進路情報の収集,整備,提供,(3)クラブ活動や学校行事などを通して生徒に自己理解を深めさせるための啓発的経験の機会を与える,(4)進路相談,(5)進学指導及び就職指導,(6)卒業後の追指導,等が考えられる。進路指導は職業指導と進学指導をともに含むものであるが,昭和33年以前においては単に職業指導と呼ばれており,中学校・高等学校において,卒業後就職を志す生徒のための就職斡旋の活動と考えられていた。しかし高等学校及び大学への進学率が飛躍的に高まった今日の進路指導においては,進学指導の比重が高まっている。特に大学・短期大学などへの進学指導においては生徒の学力偏差値が重視され,その結果として不本意入学の傾向が助長されていると批判されている。この状況を是正し生徒の能力・適性を尊重して個性に応じた適切な進路指導を実現することが課題である。